『夜明け前』の「電気情報通信」
いわゆる「幕末・明治モノ」の中で圧倒的な存在なのが島崎藤村の「夜明け前」だ。この文学作品に凝縮された迫真の歴史スペクタクルに「電気情報通信」は姿を現すか? もちろん、それは極めて印象深い場面で登場し、その姿は感動的ですらある。
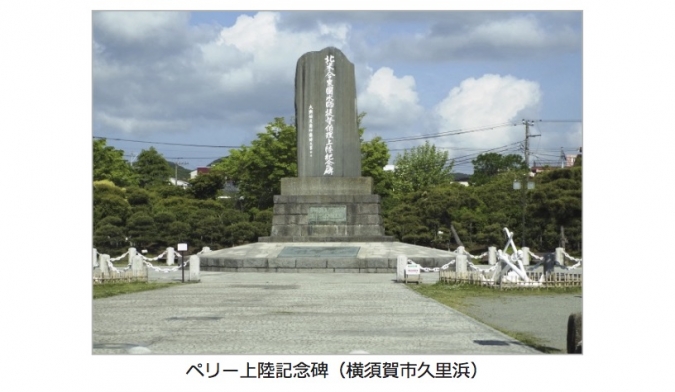
この物語のスタートはペリー来航の嘉永六年(1853年)、主人公は東山道、すなわち中仙道、馬籠宿の本陣・問屋にして庄屋の青山半蔵。この主人公と彼に繋がりのある様々な人間の視線と振る舞いを通して、明治十九年(1886年)まで、都合30年余の激動の歴史、と言うよりも日本と日本人の変化を描き出している。そしてこの作品の主題は、こうした歴史物語を越えて、それらを背景とした人間の心のもっとずっと奥深いところを追い求めている。
しかし、今、ここではその背景の一角を飾る「電気情報通信」に焦点をあて、心の中にまでは踏み込まない。筆者は『「幕末・明治モノ」に覗く「電気情報通信」』というテーマでやや趣味的な6回のエッセイを寄稿してきた。その話題は、徳川昭武と渋沢栄一のパリ万国博派遣とひきつづいた欧州巡行、これに途中から合流した栗本鋤雲の紀行文、久米邦武の記録による岩倉使節団の世界旅行、松代の象山神社で知った佐久間象山の電信実験と省諐碑(せいけん碑)、そして薩摩藩による英国への秘密留学生派遣などだった。「夜明け前」にはこうした歴史イベントはほとんど漏れなく時系列で登場する。栗本鋤雲に至っては早くから喜多村瑞見の名で本人が現れ、随所で物語進行の脇役を演じている。久米邦武についても、この物語の主人公が国学の平田篤胤没後の門人の一人だった事から、いわば国学者を代表した使節団員派遣の話しとして、主人公の感情を重ねた特別な記述がある。
「夜明け前」は二部構成になっている。このうち第一部は大政奉還、王政復古の大号令で終わる。さすがに第一部では電気通信はおろか電気そのものが登場しない。この期間、つまり参勤交代の時代、街道の往来には凄まじいものがあった。
たとえば、嘉永六年(1853年)ペリー来航のあと、江戸出府中の尾張藩家中、あるいは彦根藩などの家中の面々が続々西行した。
安政元年(1854年)、黒船再度の来航、新任の長崎奉行・水野筑後が西行。追って、尾州藩主・徳川慶勝が出府した。このときの行列は、宿場の人助2,500人、馬180匹、馬方も180人という規模だった。西から諸大名続々出府する一方、永井岩之丞のように長崎へ西行する者もいた。余談だが、あの三島由起夫の高祖父だ。
文久元年(1861年)、和宮内親王が御降嫁した。
行列の規模は藩主出府の時の比ではなかった。
文久三年(1863年)、人の流れは再び西へ。尾州藩主が上洛、新撰組が上京した。そして参勤交代の廃止。諸大名上京。江戸の諸藩主家族方帰国。十四代将軍が大阪で薨去し、京都より還御、諸役人東行した。
さらに尾州藩主、徳川茂徳参府と帰国、ついで、水戸浪士、天狗党の大規模武装西行、などなど、街道の状況は日本の歴史そのものを極めて高感度に反映していた。
馬籠宿では江戸の情報は京都より早く、京都の情報は江戸より早く入るが、いずれも数日のタイムラグがある。それはもっぱら街道を往来する人間の口づてや飛脚便によるうわさや様々な文書である。主人公の平田門人ネットワークから書簡や、時には相互訪問の形で江戸や京都、そして街道筋の情報が伝えられる。情報伝達では書簡だけでなく、重要文書の筆写の閲覧というのも大きな役割を果たしている。あちこちで重要文書が筆写され、然るべき人物のところでこれを見せてもらうという場面がある。
物語の主人公達は宿場を預かる者として、この猛烈な人と物資の往来、情報の伝達を、公に仕えるという気持ちを持ちながら支え、めまぐるしく行き交う情報の中で変化の波にもまれて行くことになる。
「夜明け前」はこうした主人公達の振る舞いと経験によって時の推移が描かれてゆく部分と、著者が背景となる時勢を直接解説する部分が交互に折り重なって進行する。第二部のはじめにかなりの紙数を割いた時局解説が置かれ、ここに、ペリイの浦賀来航時の詳細がある。その中に次の記述がある。
『彼は・・・・当時の日本人が怖れるところを利用することにかけては全く無遠慮なアメリカ人であった。ともかくも彼は強い力で、その目的を果たした。電信機、機関車、救命船、掛け時計、農作機械、度量衡、地図、海図、その他当時の日本には珍奇な贈り物を残して置いて、この国を去った。』
開国を迫るペリイの日本恫喝のための贈り物の筆頭に「電信機」が挙げられている。これは人や物資の交通路・輸送路でもあり同時に情報の要路でもある街道の物語にとってさりげない布石になっている。
追って、最初の米国領事ハリスの口上書というのが長く引用されている。これは安政四年(1857年)、将軍謁見後のハリスが掘田備中守の役宅で述べた口上の趣ということである。この中に次の一節がある。
−−五十年以前より、西洋は種々変化つかまつり候。蒸汽船発明以来、遠方かけはなれたる御国もごく手近のよう相成り申し候。電信機発明以来、別して遠方の事もすみやかに相わかり、右器械を用い候えばワシントンまで一時の間に応答出来いたし候。……
諸方の交易もいよいよさかんに相成り申し候。右様相成り候ゆえ、西洋諸州いずれも富み候よう相成り申し候。……
翌年、幽閉中の佐久間象山が京都の梁川星巌へ送った手紙の内容と符合するような話だ。
ハリスは世界情勢を説明しながら領事館設置を求め、またイギリス、フランス、ロシアを牽制し、身勝手に米国との交易の利点を強調していた。海底ケーブルはまだ発展途上だったので多分に法螺も含まれていたようだが、飛脚船と電信を駆使することで世界の情報伝達が格段に進歩していたのは事実である。米国はこれらの情勢を日本への圧力の素材とした。
「夜明け前」第二部を通して、主人公達の生活空間、街道、宿場、そして日本の諸制度は激変する。彼ら、彼女らの視界の中では多くのものが失われていった。
諸藩の軍制、諸制度はなくなった。『二百年間の繁文褥礼の廃止』、と表現されている。こまごまとして煩わしい規則・手続き・礼儀作法が消えた。旗本八万騎は洋式の陸軍隊になりフランス人の教官に託された。
江戸の大名屋敷の主は皆あわただしく帰国した。
街道筋の人々を苦しめた無賃公役はなくなり、関所も廃された。一方物価騰貴も著しかった。
東北戦争ののち、身分、世襲、主従関係の打破、一切の封建的なものの打破から、廃藩へと繋がった。街道では、道中奉行所がなくなり、新組織が設置され、様々な助郷が廃され、残っていた弊習が改められた。
『革新につぐ革新、破壊につぐ破壊』との表現だ。問屋も廃止、会所も解散、父祖伝来の名誉職のような旧い家業は消え、主人公は役職も名誉職もなくなった。
太陽暦が採用され、一切の封建的なものが総崩れに崩れて行く。本陣、脇本陣はなくなり、役筋ととなえて村役人を勤める習慣も廃止。庄屋、名主、年寄り、組頭、すべて廃止され、庄屋名主らは戸長、副戸長として、土地、人民に関することを担い、輸送に関することは陸運会社に委ねられた。
廃藩に伴い、旗本諸大名の保護を仰いでいた一芸をもって門戸を張っていた者達は、主人と運命をともにした。街道にはこうした人々の往来も見られた。
木曾の山で生活していた人々は官有林になって山林を利用できなくなった。
やがて切手を貼る郵便が登場する。本陣の一つが郵便御用取次所になった。主人公が戸惑いながら切手を貼る場面がある。
そしてこの物語の終盤、明治十三年(1880年)、「帝」の東山道御巡幸というビッグイベントが起こった。「帝」、この日本に大変化をもたらした王政復古の大号令のその本人である。主人公、青山半蔵は思いがけなくも自分の住居、旧馬籠本陣に「帝」を迎えることになった。平田篤胤没後の門人の主人公にとって『まったく夢のようであった。』
御巡幸の準備のために先発隊が到着し、道路の修繕もはじまる。そして、
『この地方では最初の電信線路建設の工事も施された。』
さらに街道の皆が準備を進めていると、
『六月二十四日はすでに上諏訪御発輿の電報の来るころである』、となる。宿場の人々は「電報」によって近づいてくる「帝」行幸の様子を教えられながら、準備に余念がないという状況となった。
「夜明け前」で「電報」はこのあともう一度、終幕に登場する。
島崎藤村はこのスケールの大きな歴史物語の中に、失われていったもの、そしてまた変わらぬものの姿を味わい深く、くっきりと彫り込んだ。そしてさらに新しく現れたものも描き出した。ここ木曾の山中では鉄道の姿は気配はあってもまだ遠かった。その中で物語の著者は、街道の旧来の姿を置き換えてゆくものの象徴として、「電信」をきらりと光る宝石のように、歴史の大壁画の中に埋め込んだ。
(神谷芳樹のオフィシャル・エッセイ)